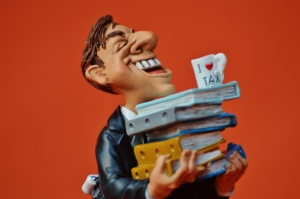この記事では、マイクロ法人におすすめしたい事業(業種)を、具体的にご紹介します。
個人事業である程度の利益があれば、マイクロ法人の設立により、節税や社会保険料を削減できる可能性が高いです。
しかし、いざマイクロ法人を設立すると言ってもどのような会社を作ればいいのか、また、どのような事業(業種)がいいのか、よくわからないのではないでしょうか。
そこで、具体的な業種や職種までご紹介するので、マイクロ法人で節税したい人はぜひ最後まで確認してくださいね。
まずは確認!マイクロ法人による節税の概要

念のためまず最初に、マイクロ法人設立の節税の仕組みについて簡単に確認しておきましょう。
- 売上の一部をマイクロ法人に移す
- マイクロ法人側で低めの役員報酬を取る
- マイクロ法人側で社会保険に加入
マイクロ法人を設立した節税は、上記のような手順で行います。
個人事業主とマイクロ法人の二刀流で事業を分けて管理しますが、マイクロ法人の作り方やより具体的な解説は、「マイクロ法人の作り方や社会保険料の削減の流れ!売上なしや赤字は違法かについても解説!」をご確認ください。
マイクロ法人におすすめの事業(業種)を具体例に沿って解説!

- 複数の収入源がある(見込み含む)
- 周辺業務への事業拡大が容易
- 現時点で個人事業の所得が高額
- 法人への事業引き継ぎが容易(契約など障壁がない)
マイクロ法人におすすめの業種のいくつかの特徴として、上記のような特徴があげられます。
すでに説明したように、マイクロ法人を設立する最大のメリットは、社会保険料の削減をはじめとした節税です。
その効果が発揮しやすく、マイクロ法人の節税が馴染みやすい事業をいくつかご紹介します。
念のためですが、法人側に取引実態のないような場合は税務署に租税回避行為として否認される可能性があるため注意しましょう。
法人側で計上する事業はしっかり個人のものと住み分けし、合理的な根拠と基準により分離して継続適用しましょう。
そのため無理なく継続できるものを選びましょう。
それでは具体的にいくつか紹介していきます。
マイクロ法人におすすめな具体的事業(業種)①:フリーランス全般
「プログラマー」や「デザイナー」、「コンサルタント」などの事業をまとめて紹介させて頂くため、フリーランス全般としました。
これらの業種で収入が複数にまたがる場合には、マイクロ法人の設立による節税が馴染みます。
また、社会的信用の向上なども営業面で役立つ可能性が高く、しっかりメリットを享受できそうです。
フリーランスで活躍中の人で、所得が大きくなってきてる人は、検討してみるといいでしょう。
マイクロ法人におすすめな具体的事業(業種)②:せどりや転売などの小売り
最近ではせどりや転売などのビジネスで高額の収入を得る人も多くなってきています。
そのような場合も、マイクロ法人を利用した節税がおすすめできる事業です。
せどりや転売もある程度の規模感が出てくるとコンサルなどのビジネス展開を並行される場合も多く、個人と法人での事業の住み分けもしやすいからです。
アカウントの引き継ぎや古物商の再取得など、場合によっては手間もかかりそうですが、節税メリットは高いため検討してみるといいでしょう。
マイクロ法人におすすめな具体的事業(業種)③:ブログやアフィリエイト
ブログをはじめとしたアフィリエイト系の広告収入も、マイクロ法人の設立に向いています。
この場合も複数の収入源が混在するケースが多く、マイクロ法人での運用がしやすい業種と言えます。
また、収入も思いのほか高額になる場合も多いため、個人に収入が集中し、かつ社会保険も個人向けの保険の場合は高額になるため、マイクロ法人を利用すれば節税効果は高いです。
ある程度収入を得られるようになれば、情報配信や教材系の商材、あるいはコンサルティングなどにも発展させやすいため、将来的な部分まで視野に入れても、マイクロ法人が一つあればかなりコントロールしやすくなる業種と言えそうですね。
マイクロ法人におすすめな具体的事業(業種)④:YouTubeなどのSNS
YouTubeなどのSNSで収入を得ている場合も、マイクロ法人での節税が役立つ場合があります。
最近ではかなりの高額収入を得る人も増えてきています。
これらの収入は、YouTubeなどSNSから直接入ってくる収入の他、広告主からの収入、あるいは企業のアカウント運用やコンサルティングなど多くの収入源に発展する場合が非常に多いです。
そのため、マイクロ法人を設立して売上の一部(一部の事業)を移管することで、上手に節税する事ができるでしょう。
YouTuberなどSNS系の事業もかなりマイクロ法人の設立がかなり馴染む業種と言えます。
マイクロ法人におすすめな具体的事業(業種)⑤:不動産
不動産系の事業もマイクロ法人での節税が可能です。
不動産の場合は、同じ業種でも個人事業主と法人で並行しやすい珍しい業種と言えます。
例えば物件ごとに分けて個人と法人で同じ業種を営むケースもすごく多く、他の業種ではあまり考えられませんが、「投資」としての側面も強く、特殊な業界と言えます。
場合によって取得した不動産を売却するような際にも、個人の場合は保有期間が5年以内だと40%近い税率になりますが、法人の場合はかなり低い税率でおさえられるため、お得感があります。
そのため、不動産はマイクロ法人を使った節税にはすごく相性がいい業種といえるでしょう。
マイクロ法人おすすめの事業(業種)⑥:太陽光発電
太陽光発電の売電収入を狙った事業も、マイクロ法人を利用した節税が利用しやすい業種と言えます。
なぜなら、たいていの場合は他に収入源がある場合が多く、住み分けがし易いからです。
さらに大抵の場合は安定的な収入になるため、計算もしやすく、かなり計画的な節税が可能になりそうです。
太陽光発電事業をされている場合は検討の余地がありそうです。
マイクロ法人の節税はその事業(業種)に詳しい税理士さんに相談しよう!
マイクロ法人におすすめの業種を紹介しましたが、具体的なシミュレーションや運用方法などについては、専門家に相談するのが最も安心です。
特に、特定の業種に詳しい税理士さんへの相談が最適と言えそうです。
まだお決まりで無いようでしたら下記で紹介していますので、よければ確認してみてくださいね。
【まとめ記事】
税理士紹介サイトおすすめランキング
税理士さんの探し方
【口コミ記事】
税理士紹介エージェントの口コミや評判
税理士ドットコムの口コミや評判
税理士紹介センタービスカスの口コミや評判
マイクロ法人におすすめの業種や事業内容についてまとめ
- 複数の収入源がある(見込み含む)
- 周辺業務への事業拡大が容易
- 現時点で個人事業の所得が高額
- 法人への事業引き継ぎが容易(契約など障壁がない)
- フリーランス全般
- せどりや転売などの小売り
- ブログやアフィリエイト
- YouTubeなどのSNS
- 不動産
- 太陽光発電
今回はマイクロ法人におすすめの事業(業種)について紹介してきました。
事業の特徴や具体的な事業内容など、マイクロ法人を検討している方はぜひ参考にしてくださいね!